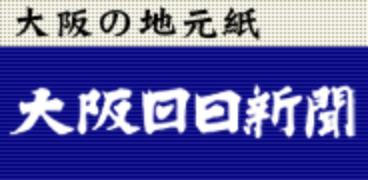金井啓子の伴走で伴奏

懐の深い新聞での自由な執筆 コラムで得た出会いという宝物

世代間で引き継ぐ味や伝統 私は何を伝えられるか

進まない海外パビリオン建設 試されるプロか素人の違い

自分の頭で考える人間に 原因は今までの教育か

母の旅立ちにいま思うこと 別れの過程を徐々に歩む

新聞は冬の時代から氷河期へ それでも消えない役割と使命

維新がハラスメント研修を開催 大切なのは個々の自覚と持続

冬の時代に気を吐く「文春砲」 伝えるべき情報逃さず

議員数増加だけが成長ではない 必要な党と議員の真摯な反省

万引の事実を報道で終わり? 求められる背景と原因の分析

実家じまいに感じるさびしさ 思い出を形あるまま残せるか

マスク着脱の同調圧力続くか きょうから5類引き下げ