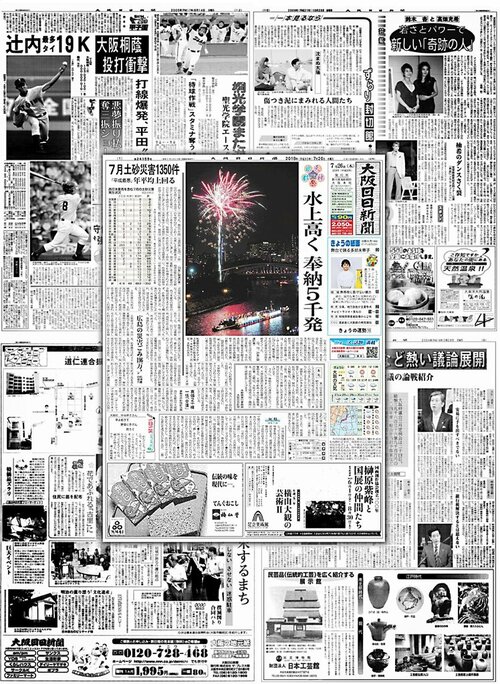日日、町を歩く。
日日、人に尋ねる。
日日、記事を書く。
同じことの繰り返しのような毎日に、
さまざまな「好きやねん!」、
たくさんの「何でやねん!」を見つけた。
日日、心が躍った。
日日是好日。
今までも、これからも-。
よりよい社会を考える
藤木俊治記者
「記者が記事を考えることは、よりよい社会を考えることにつながっている」。駆け出しの頃、取材対象者として面会したことがきっかけで交流が始まった、元大手紙記者の大先輩からもらった言葉だ。
入社後、訳も分からないままペンとノート、首からカメラをぶら下げて現場に出向いた。初めて掲載された記事は、福沢諭吉が生まれた大阪・福島の中津藩蔵屋敷に関する話題。署名が紙面に載る重みを初めて感じた20年ほど前のことを今も覚えている。
以降、行政、司法、企業、スポーツ全般、「アスファルトから『ど根性ネギ』が生えてきた」などといった“どローカル”な話題まで、担当したすべてが財産になった。
街頭では、厳しい評価をいただく一方、「昔、紙面で取り上げられた」と喜んでもらえることも多かった。「大手が取り上げない話題」を深掘りすることを肝に銘じてきたが、どれだけ読者の皆さんのお役に立てただろうか。
ネット全盛の今、紙媒体の温かみが失われるのは発行元としても一抹の寂しさがある。紙面はなくなっても、「よりよい社会を考える」という視点は決して失わずにいたい。
大和都市管財事件で国賠訴訟
木下功記者
自分が書いて印象に残っている記事に、2001年7月19日付で1面と社会面に展開した「大和都市管財事件」に関するものがある。
第二の「豊田商事事件」と呼ばれた抵当証券会社による巨額詐欺事件であり、1面で被害者弁護団が同社役員に対して損害賠償請求を行うことを報じ、社会面で弁護団長と同社の監督官庁である近畿財務局幹部のインタビューを掲載。後に行われる国家賠償請求の可能性を示唆した内容となっている
入社の年であり、1面トップの記事を書いたのも初めてだったが、印象が強い理由は別にある。
もともと、前の会社の先輩が筆者の転職の手みやげにと事件が明るみに出ることを教えてくれていた。しかし、私は警察につてがなく、発生時に記事を書くことができなかった。このままでは先輩に対しても顔向けできないと、弁護団や監督官庁への取材を重ね、何とか掲載できた記事である。
もう一つ。2016年6月に母が他界した。仏壇を整理していた際に、母に送った手紙や弟の小学校時代の絵日記といっしょに、15年前の記事の切り抜きが出てきた。息子が初めて書いた大きな記事を喜んでくれていたのだと思う。
黒猫との出合い
北野保司記者
入社1年目の暮れ、正月特集ページを担当することになり、かねて母から相談を受けていた鶴見緑地の野良猫をテーマにした。
動物を捨ててはいけない。ただ野良猫を世話する人への批判もある。動物虐待事案も発生していた。どうまとめるか算段がつかないまま、公園に通う中で一匹の黒猫に出合った。
生まれて間もないようで、目が開いていなかった。いつもコンクリートの上で寒風に耐えるようにじっと縮こまっていた。この子を撮るだけで、伝わるものがあるのでは。最後の取材日にレンズを向けると、か細い声で鳴いた。
特集ページをきっかけに多くの人から「ちょっと聞いてや」の声をいただくようになり、ありがたかった。紙面を飾った子猫は、母の強い意向でわが家に迎え入れられ、その後毎朝、私の顔をなめ回す係になった。
あれから20年。たまに実家に帰ると手をなめてくれた老猫が、今年5月にこの世を去った。偶然とはいえ休刊と重なった別れはもの悲しく、「さあ行け」と背中を押されているようにも感じている。
新聞の価値かみしめ
斎藤架奈枝記者
「まるで魑魅魍魎(ちみもうりょう)が跋扈(ばっこ)する魔窟だ」(森絵都「みかづき」)。しのぎを削る同業者の会合の雰囲気を端的に表した言葉だ。これまで使ったことがない言い回しなどを見つけるたびに手帳に記してきた。
真実を確実に、客観的に、分かりやすく、極限までそぎ落として。しかし、“ひな型”通りに排出するマシンになってはならぬ。そう戒め、さらに「誰かの人生を変えるくらい力のある記事」を1本でも2本でも書き上げることを目標に執筆してきた。
誰もが“新人”からスタートする新聞記者という職業。昔の原稿を読むと、先の手帳を活用したのか、こなれていない表現が目に付くものもある。だからといって、その青臭い原稿より今の方が良作か、というとそうとも言い切れない。
いざベテランになると、経験や知識を積んだ分だけ視野も人脈も広がり、原稿を仕上げる要領も良くなった。しかし、新しい事へのときめきや情熱は昔のそれには確実に及ばない。
新人とベテランだけでなく、個々人持ち味が違う多種多様な人間が書く原稿が毎日一緒くたに載る新聞という媒体は、実は他には代えがたい面白さと希少さがあるとつくづく思う。さて明日から、どの新聞を届けてもらおうか。
ギネス級?連載終了に涙
松村一雄記者
今シーズンからメジャーに活躍の場を求め、アスレチックスからオリオールズにトレードで電撃移籍した藤浪晋太郎投手が大阪桐蔭高の、その年の高校球界の大エースだった2012年の夏、舞洲球場のバックネット裏での何げない言葉のキャッチボールがロングラン連載につながった。
その連載が「大阪モデルコレクション」で、その雑談の相手がフォトグラファー霜越春樹さん。お互いが藤浪投手の躍動をカメラに収めるために熱中症と戦っている時だった。隣り合わせになったのは偶然か必然かは覚えていない。
トントン拍子に話は進み、その年の秋から大阪のモデルシーンを盛り上げようと連載スタート。途中、コロナ禍で休載を余儀なくされたが、各方面からの最大の協力をいただきながらギネス級(?)の回数を重ねることができた。最後は駆け足になったがその回数は実に500回。
正月紙面を彩るために晴れ着でのロケも懐かしい。登場してくれたモデルたちから聞こえてくる感謝の声がうれしい。そして霜越さんとのタッグが10年以上続いたことも誇り。いつかどこかで501回をともくろんでいる今日この頃。
カメラの変遷、懐かしきシャッターの緊張感
佐々木誠記者
自分が撮影した写真が初めて紙面に載った時の感激は今でも鮮明によみがえる。記念すべき“初の被写体”が、ある催しに招かれた歌手・八代亜紀さんだったことも印象的だった。当時はフィルムカメラ全盛で使用機種は「ニコンFA」。装着していたレンズやストロボまで細かく覚えているのが面白い。
社内の暗室でフィルム現像や焼き付けといった作業も当たり前の時代。「1画素=1万円」といわれた高価な業務用デジカメの黎明(れいめい)期となり、メーカーから白黒専用のデモ機を触らせてもらったが、まだ記録画像をすぐに確認できるような段階ではなかったこともあり、今日のようなデジタル全盛時代が到来するとは夢にも思わなかった。
後年、ようやくコンシューマ向け機種が市場に出回る時代となり、初めて写真特集面の全カットをデジカメで撮り終えた際は何とも手応えのない、極めて無機質な感覚であったことも忘れがたい。
今やスマホで写真や動画が高画質で撮れる万能の時代にあって、一部では温かみのあるフィルムの写真が話題に上ることも。現状でフィルムカメラで取材する機会はないが、1本で最大36枚という撮影枚数も含め、かつての緊張感はいつまでも胸に刻んでおきたい。