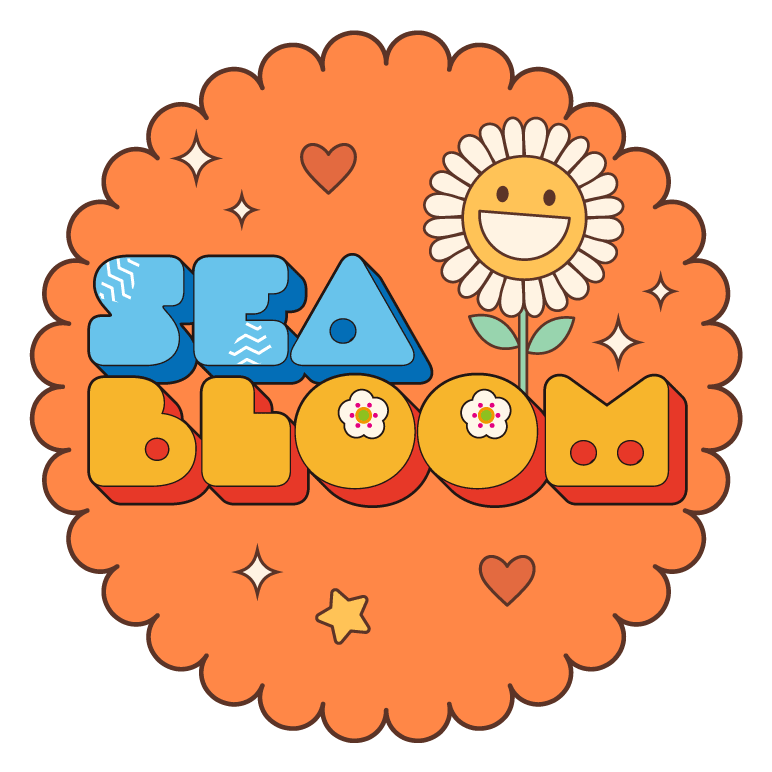ヘルマン・ヘッセ(1877~1962)が青春の苦悩を抒情的に描いた自伝的小説『車輪の下』(1906年)を読むことはある一時期、いやかなり長い間、思春期の通過儀礼のようなものだった。少なくとも私が10代半ばのころ(既に半世紀以上前のことだ)は確かにそうだったし、おそらく、それ以前もそれ以後も、この位置付けはあまり変わらずに続いてきたのではないだろうか。
しかし、ヘッセを読み続けて『荒野のおおかみ』(1927年)にまで至る人はそう多くなかったと思う。こちらは五十絡みの男の屈折した内面に目を向けた、皮肉っぽく、幻想的で、そしてエロティックな小説である。今回取り上げようと思ったのは、主人公が幻覚の中でモーツァルトに出会う場面があるからだが、まずは同書が1960~70年代のアメリカで若者に大きな影響を与えたということから始めたい。ヘッセの愛読者やカウンター・カルチャーに詳しい人々以外にはあまり知られていない、あるいは忘れられている事実だと思うので、長い前置きになるがお許しいただきたい。
1971年に出た新潮文庫版の解説で、訳者の高橋健二が「一九七〇年のアメリカの若者が、『荒野のおおかみ』に共鳴...