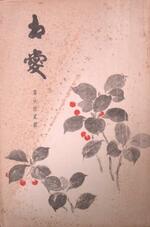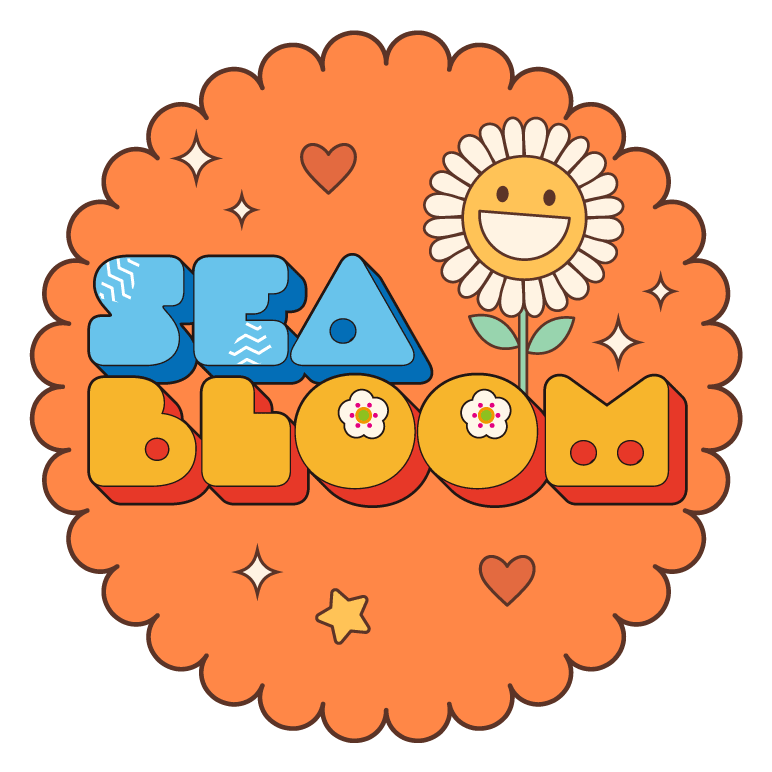作家の山崎豊子(1924~2013年)は大阪・船場の老舗昆布商の家に生まれ、作家として独立した頃から亡くなるまで堺市に暮らした。私自身、2010年に自宅を訪ねてインタビューしたことがある。その堺に2015年にオープンした文化施設「さかい利晶の杜」で企画展「堺に生きた山崎豊子のまなざし―愛用品の数々―」(5月29日まで)が開かれていると聞き、5月18日に大阪に向かった。
この日を選んだのには、訳がある。相愛大人文学部教授の荒井真理亜の講演を聞きたかったのだ。演題は「山崎豊子の文学的出発―新資料から見えてくること―」。新資料とは何か、そこから見えてくることとは―。それが知りたかった。
■橋は焼かれた
山崎のデビュー作は、生家をモデルに書いた小説「暖簾」である。戦時中の1944年に京都女子専門学校(現在の京都女子大)を卒業し、毎日新聞大阪本社に入社した。最初は調査部にいたが、45年に学芸部へ異動。そこで当時、学芸部副部長だった井上靖(1907~91年)に出会う。
井上はすでに作家としてデビューしていた。新聞記者として働きながら小説を書き続ける井上の姿を見て、山崎は心を動かされたようだ。山崎...